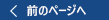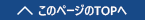ホーム > 航空救難団の活動 >隊員の活動>機上整備(UH-60J)
機上整備(UH-60J)
松島救難隊 2等空曹 小西 祥文

航空自衛隊のUH-60J救難ヘリコプターの機上整備員(FE:フライトエンジニア)は、飛行に必要な各種性能データの算出、飛行中のシステム監視及び不具合発生時の助言などを行う「コックピット業務」と、遭難者の捜索、救出のためのホイスト操作及び救出後に救難員が行う負傷者の応急手当をサポートする「キャビン業務」を行っています。また、地上において軽易な航空機整備作業を行うこともあります。
まさに、整備員、パイロット、救難員の架け橋的存在であり、航空機システムから捜索救助に関わる幅広い知識、過酷な環境において各種救助作業を行う技術、体力及び精神力が求められます。
UH-60Jの機上整備員になるためには、ヘリコプター整備員として1年以上の経験を積んだのち、選抜試験を受けて合格しなければなりません。選抜試験に合格した隊員は、愛知県の小牧基地にある救難教育隊での「機上整備(回転翼)員課程」において約5か月間の教育を受けます。卒業後は、全国の部隊において更に訓練を積んだのち、任務に就くことになります。

Q.機上整備員になろうと思ったきっかけ教えてください。
A.救命装備品整備員として浜松救難隊に所属していたとき、災害派遣等に向かうクルーを見送っているうちに現場に向かえない自分に悔しさを感じ、その時の経験から、私自身が救難現場の最前線でより多くの人々を助けたいという思いが、きっかけになりました。
Q.機上整備員として特に努力したことがあれば教えてください。
A.元々がヘリコプター整備員ではなく、機体をほとんど取り扱わない特技であったため、受験資格を得るため約2年間、一から機体のシステム及び取り扱い等の勉強をしました。そして、様々な作業を実施しながらパイロットに助言する必要があるため、マニュアルを片手にというわけにはいかないので、いまでも航空機のシステムに関する知識を身につけ、技能の習得に努めています。
Q.機上整備員になって1番印象に残っていることは何ですか?
A.初めての災害派遣です。台風19号に関わる災害派遣の任務でした。不安と緊張が大きかったのですが、任務を無事に終えたときの達成感はひとしおで、13年越しの目標が達成できた瞬間であり、機上整備員としての第一歩を踏み出せたと感じました。
Q.機上整備員になってよかったと思うことがあれば教えてください。
A.要救助者を救助するため航空機に搭乗し直接現場に赴くという長年の夢が今では、自身の任務となっていることです。責任は大きいですが、その分大変やりがいを感じています。
Q.今後の目標を教えてください。
A.機上整備員になってまだ2年弱と日が浅いこともあり、更なる自己研鑽に努めて、いかなる環境の救難現場でも冷静に任務を達成出来るようになり、クルーから信頼される機上整備員になりたいです。