

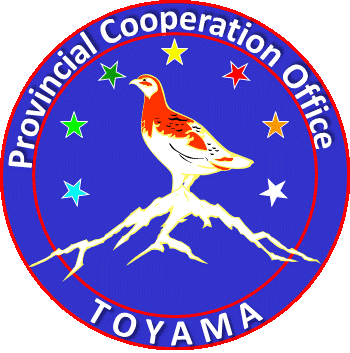




H7.3 第13戦車大隊(日本原)
H11.3 第13戦車中隊(日本原)
H12.3 第10戦車大隊(今津)
H14.3 第10偵察隊(春日井)
H15.8 指揮幕僚課程(目黒)
H17.8 第13特科隊(日本原)
H18.3 第14戦車中隊長(日本原)
H20.3 第7師団司令部第3部(東千歳)
H21.8 陸上幕僚監部人事部厚生課(市ヶ谷)
H24.3 北部方面総監部防衛部防衛課(札幌)
H26.8 幹部高級課程、統合高級課程(目黒)
H27.8 第7師団司令部第3部長(東千歳)
H29.8 第11普通科連隊長(東千歳)
R1.8 教育訓練研究本部訓練評価部(目黒)
R2.3 評価支援隊作戦評価分析第2科長(北千歳)
R4.12 現職(富山)

本部長 1等陸佐 宮内 雅也
皆様こんにちは。当ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
先般ホームページを一新しました。見やすさ、使いやすさ、分かりやすさ等を考慮し完全リニューアルしましたのでどうぞご活用して下さい。それもあり当コンテンツも月一のペースで更新していきますのでどうかご覧下さい。
今回は、私の幹部候補生から初級幹部(2・3尉)時代のお話をさせて頂きますが、ご覧になられた方には、些細なことに一喜一憂(特に一憂)せず一度決めたことには努力を続けてもらいたいというお話です。
私は関西の某大学から陸上自衛隊の一般幹部候補生として、福岡県久留米市にある幹部候補生学校に平成6年4月に入校し、自衛官人生をスタートさせました。大学生時代は特段の運動をしていたわけでもなく、国防の念にかられて入隊したわけでもなかったため、正直やっていけるかどうか不安に感じながら着校したことを覚えています。
当時の教育期間は2月中旬までの約11カ月でしたが、実は5月中旬から約2カ月の間、右膝の前十字靭帯断裂と半月板損傷のため入院していました。退院後もリハビリが必要で普通に訓練に参加したり運動ができるようになったのは9月末頃だったと思います。その影響もあってか卒業時の成績は下から数えたほうが早かったです。卒業から約4か月後に小隊長としての教育に約8カ月参加しましたが、当時は陸曹から部内選抜して幹部になった方々と一緒に教育を受けており、元々の素地が違うため卒業時の成績はやはり下から数えたほうが早かったです。
教育を修了し小隊長として勤務している間も、当初は分からないことばかりで戸惑うことも多く、父親と同年代の職人のような陸曹にも指示しなければならない中、周囲の色々な方に指導を受けながら、また教えてもらいながら勤務をしていたことを覚えています。当時の陸曹たちの信頼を得られたのは一年近くかかったのではないでしょうか。
幹部自衛官の自衛隊人生においては、初級幹部時代の勤務がその後の勤務の指標ともなり大いに影響するものです。当時のいろいろな苦労があって今の私があるものと考えています。若い時の苦労は買ってでもしろというのは死語でしょうが、未来ある若者には一度自らが決めたことには努力を続け、答えのない世界でも自ら答えを出すような人生を送って頂きたいと思います。何かのご参考にして頂ければ幸いです。
皆様こんにちは。当ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
また、改めまして明けましておめでとうございます。令和6年も皆様にとって実り多き一年とならんことを祈念申し上げます。
去る12月9日、富山市内のオーバードホール大ホールにて、当地方協力本部が主催する「ミュージックフェスタ 2023 in TOYAMA」が行われました。今回は、昨年度より約500名多い約2,100名のお客様にお越しいただき、海上自衛隊 東京音楽隊を招致して行いましたが、歌姫 三宅由佳莉2曹の素晴らしい歌声も相まって、非常に盛会に終了することができ、非常に成果のあった演奏会でした。お越しいただいたお客様には、この場を借りて改めて感謝申し上げます。なお、本演奏会のポスターやパンフレットのデザインは、富山北部高校のデザイン部の方々に作製していただき、本演奏会にも参加していただきましたが、これまで接点のなかった若い方々とも縁を繋ぐことができたことも一つの成果であったものと考えます。
自衛隊の中には「音楽隊」と言われる音楽演奏を専門にする部隊があり、全国各地で各種行事やイベント、部隊・隊員の士気高揚等のために活動しており、陸上・海上・航空自衛隊あわせて33コの音楽隊が各地に存在します。その数を聞いて驚かれる方もおられるかもしれませんが、自衛隊は自己完結型の組織と言われるように、よくイメージされる直接戦闘する機能のみならず、音楽演奏をはじめ、情報収集、機械整備、建設・工事、調理、警備、輸送、調達等、非常に多くの機能の集合体です。これを機に、自衛隊という組織に関心をもっていただければ有難いと思います。
さて、令和6年は、十干十二支でいえば「甲・辰(きのえ・たつ)」で、「春の日差しが、表に出ているもののみならず、日頃隠されていたものにまで寛大に広く注がれ、成長や変化を促す」といったことを意味するそうです。この「甲辰」が示すように、皆様のこれまでのひたむきな努力も報われ、大きな成長を遂げられる1年となられることを祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。