Q1 サイバー攻撃とは何ですか。また、その特徴と現状について教えて下さい。
A1 サイバー攻撃については、情報通信ネットワークや情報システム等の悪用により、サイバー空間を経由して行われる不正侵入、情報の窃取、改ざんや破壊、情報システムの作動停止や誤作動、不正プログラムの実行やDDoS攻撃(分散サービス不能攻撃)等として整理されています。サイバー空間の拡大に伴い、サイバー攻撃が行われた場合には、社会活動の広範囲で甚大な被害が生じる可能性があり、また、サイバー攻撃は攻撃源の特定や抑止が困難といった特性があり、その対応は国家の安全保障・危機管理上の重要な課題となっています。
Q2 防衛省・自衛隊はどのように対応しているのですか。
A2 防衛省・自衛隊は、自らの情報システム・ネットワークに対するサイバー攻撃に対処しています。
そのための体制として、
平成26年3月、自衛隊指揮通信システム隊の隷下に共同の部隊としてサイバー防衛隊を新編し、情報通信ネットワークの監視及びサイバー攻撃への対処を24時間態勢で実施しています。
また、各自衛隊においても、陸上自衛隊システム防護隊、海上自衛隊保全監査隊、航空自衛隊システム監査隊の各システム防護部隊がそれぞれの情報システムを監視・防護しています。
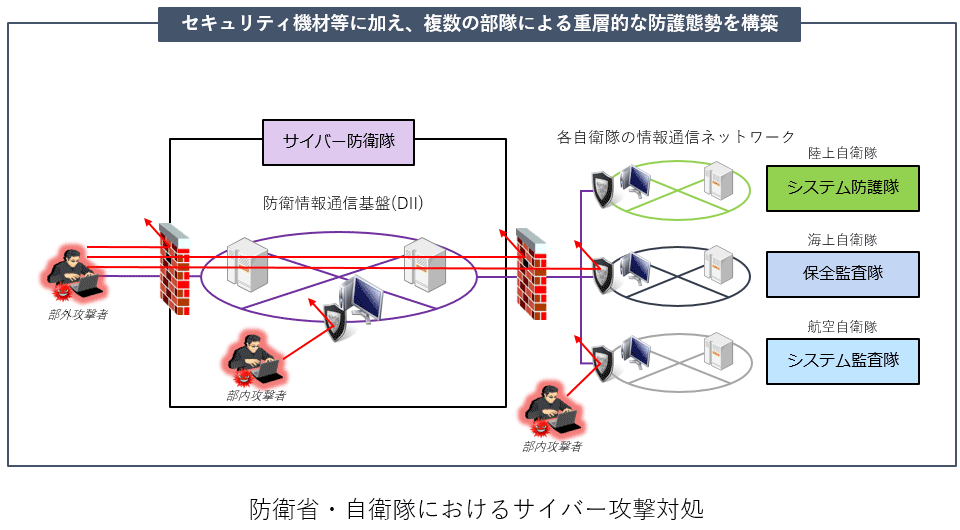
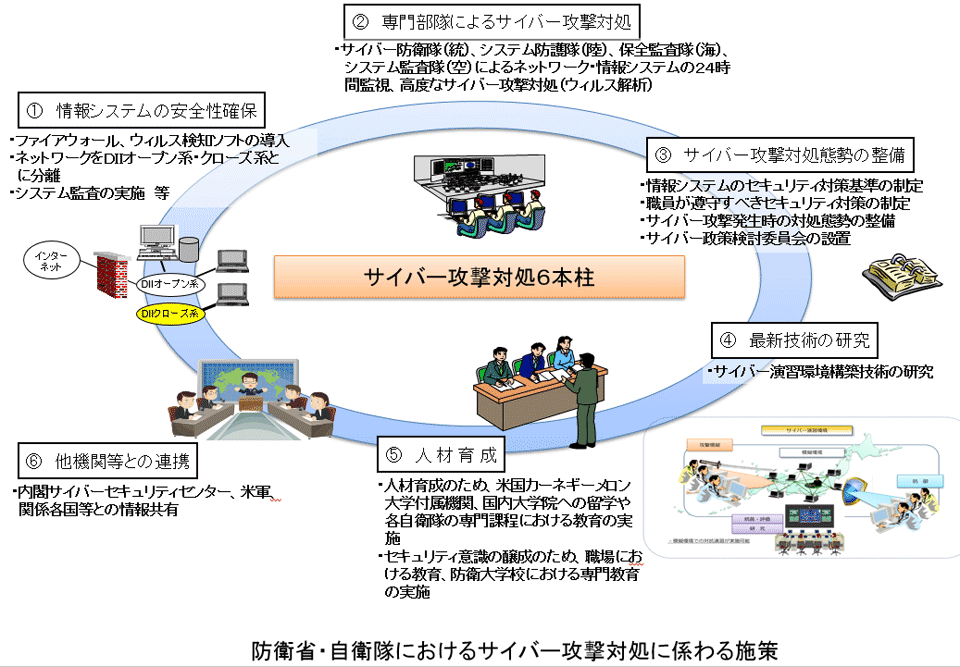
Q3 関係省庁や諸外国との間ではどのような連携を行っていますか。
A3
サイバー空間の安定的な利用を防衛省・自衛隊のみによって達成することは困難であることから、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)等関係省庁との連携を行っています。
また、サイバー空間に関する日米協力については、平成27年4月の新ガイドラインや同年5月の日米サイバー防衛政策ワーキンググループ(CDPWG)の共同声明において、日米両政府の協力として、迅速かつ適切な情報共有体制の構築や、自衛隊及び米軍が任務遂行上依存する重要インフラの防護等が挙げられているとともに、自衛隊及び米軍の取組として、各々のネットワーク及びシステムの抗たん性の確保や教育交流、共同演習の実施等について記述されているところです。こうした方向性に基づき、日米サイバー防衛協力をより一層加速していきます。
その他の国々については、英国、オーストラリア、エストニア、NATO等の関係国・国際機関との様々なレベルでの協議を通じ、情報共有等の協力を進めています。
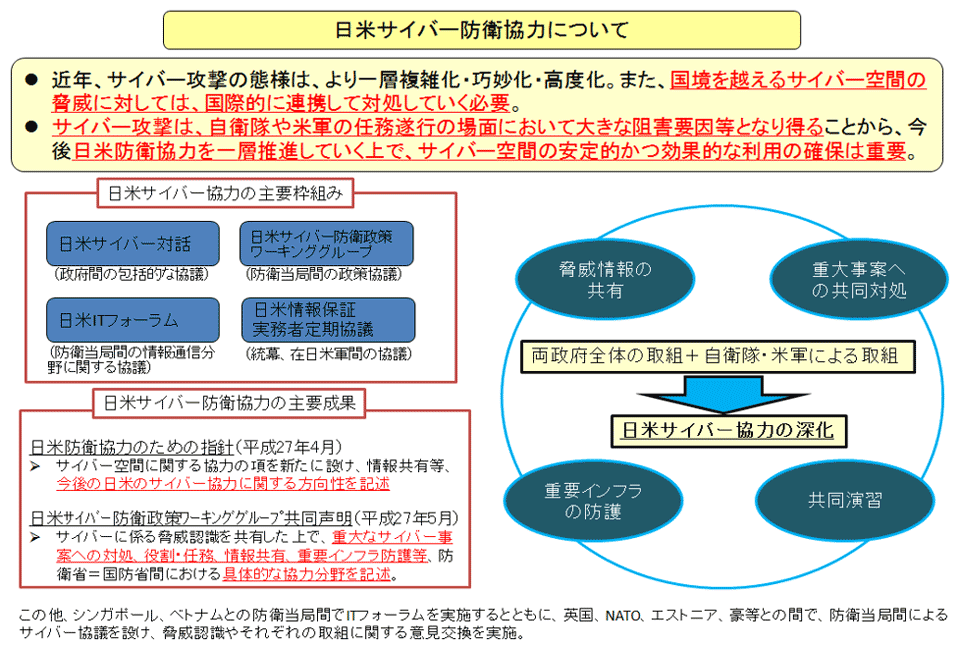
Q4 防衛省・自衛隊の今後の取組について教えて下さい。
A4
防衛省・自衛隊では、自らの情報システム・ネットワークに対するサイバー攻撃に対処するため、抗たん性の向上、情報収集機能や調査分析機能の強化、サイバー攻撃対処能力の検証が可能な実戦的な訓練環境の整備等所要の体制整備等を行い、サイバーセキュリティの確保に努めているところです。
また、サイバー人材を効率的に育成・確保することができるよう、人材育成を重視したキャリアパスの設定、教育の充実・高度化及び外部の高度人材の活用について検討を進めています。
防衛省・自衛隊として、サイバー攻撃への対処に万全を期すよう、サイバー防衛隊の増強をはじめとする対処体制の強化や人材育成・確保について、今後も計画的に検討を進めていきたいと考えています。
2017年5月22日更新